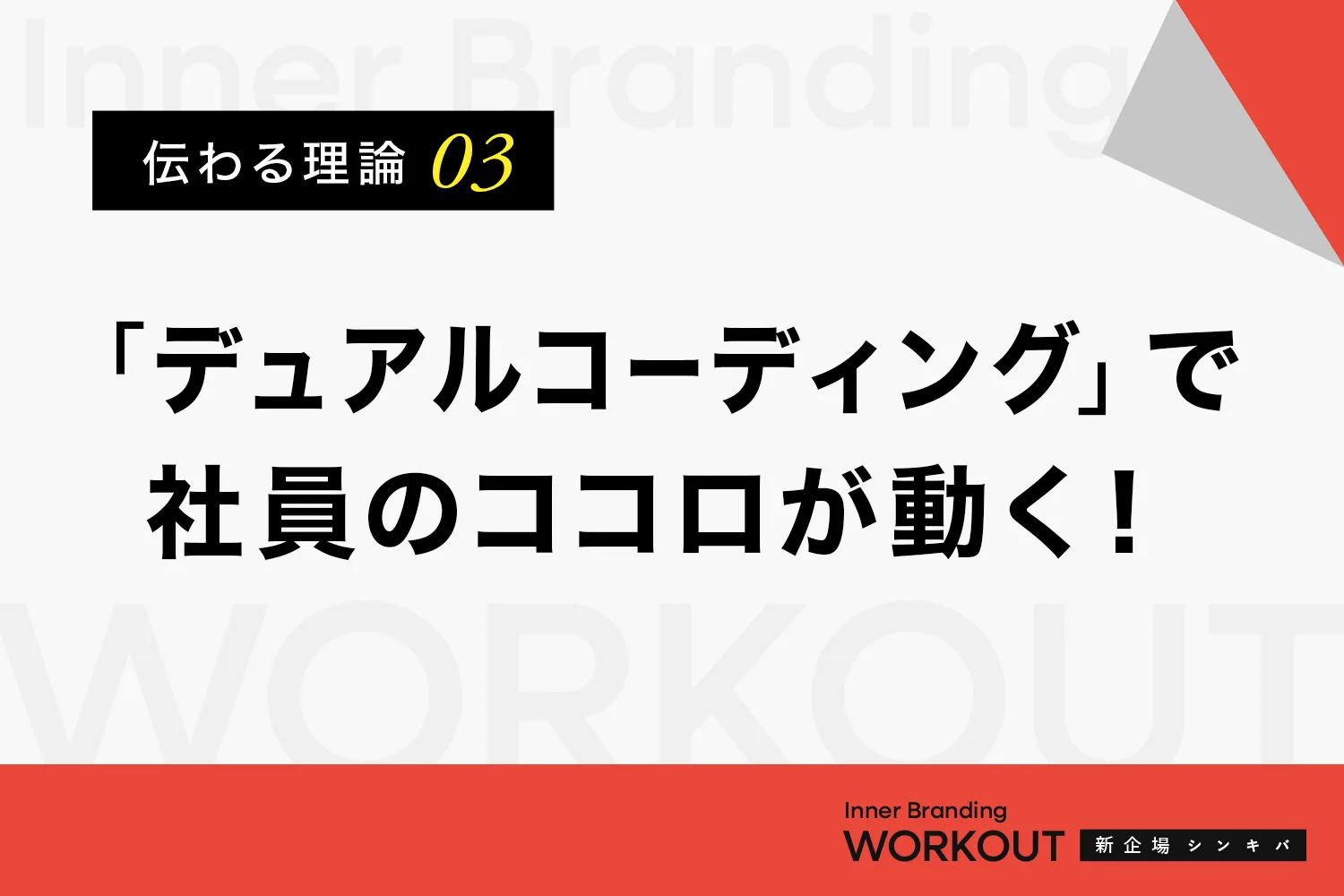参加した企業各社様に事前アンケートを実施。インナーブランディングに関する課題で「重い」と思うことに、順位をつけてご回答いただきました。その結果データをもとに、課題の重さランキングを出しました。
まず、順位を予想してもらいます。その回答は、実際に課題ごとに重さが違う重りを持って、ご自身の回答とすり合わせをしていただきました。
なぜ、実際に持ってもらうのか? そこには「伝わる」ための理論がありました。

このIBワークアウトには「⾝体性認知理論」と「デュアルコーディング理論」が使われています。
私たちの⾔語には、無意識に「重さ=重要性」の概念が埋め込まれています。
例えば「重⼤な決定」「責任が重い」「重く受け⽌める」…など。これらは偶然ではなく、脳の認知メカニズムに基づいていて「⾝体性認知理論」として確立されているのです
2009年、オランダ・アムステルダム⼤学でこんな実験が行われました。
被験者にアンケートに回答してもらうのですが、片方は、重いクリップボード(1kg)でアンケートを回答。もう片方は、軽いもの(300g)で回答してもらいます。
すると驚くなかれ、軽いクリップボード(300g)で回答した被験者より、重いクリップボード(1㎏)で回答した被験者のほうが、対象の価値を約20%⾼く評価したのです! この実験を通して、物理的な重さが、無意識に⼼理的な「重要度」の判断に影響することが明らかになったのです。これは「⾝体性認知理論」と言われ、人は体感することで伝わり方が違うことを示しています。
また、1971年アラン・パイビオが、2つの形式で情報をインプットすると記憶が強化されると提唱したのが「デュアルコーディング理論」です。
今回は「課題の重要度」と「実際のお重さ」、この2つを同時に知る、感じることで、情報のインプットの強化を促進していたのです。
こうして体験した多くの企業の方が、どの社内課題の重要度が高かったか、その順位を正確に覚えたのです。
自社の社員に「覚えてほしい」と思う事や、「感じてほしい」ことについて、単にプレゼンしたり、資料を共有するだけでは、認識度・理解度が低い可能があります。
改善するためには「なぜそうなったのか?」を感じられるリアルな映像を展開したり、あえて本音を言っている「お客様の声」を流したり、社員のココロに響くコンテンツを実施すると効果的です。